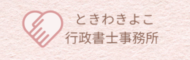- Home
- 住まいと記憶のはざまで, 連載シリーズ
- 【連載シリーズ:住まいと記憶のはざまで】第2回 家を買うという決断——還暦と年金生活のはざま」
ブログ
10.302025
【連載シリーズ:住まいと記憶のはざまで】第2回 家を買うという決断——還暦と年金生活のはざま」

第2回:「家を買うという決断——還暦と年金生活のはざま」
高齢者の賃貸住宅事情の厳しさの理由
夫が還暦を迎える今年、私たちは地方都市で中古マンションを購入するという決断をしました。
この選択には、いくつかの現実的な背景があります。
まず一つは、高齢者の賃貸住宅事情の厳しさです。
本ブログでも以前触れてまいりましたが(部屋借り短い人の支援、国が議論する家主の「拒否感」どうしよう?【気になる記事ブログ⑰】)、60歳を超えると、賃貸住宅の契約が難しくなるという現実があります。特に単身高齢者の場合、家主側が孤独死などのリスクを懸念し、入居をためらう傾向が強くなります。
事故物件となることで資産価値が下がることを恐れるためです。
📊 高齢者の賃貸入居に関する調査データ
国土交通省の調査によると、民間賃貸住宅の家主のうち、約60%が高齢者の入居に不安を感じていると回答しています。
その主な理由は以下の通りです:
| 不安の内容 | 割合 |
|---|---|
| 孤独死のリスク | 45.2% |
| 家賃滞納の可能性 | 28.7% |
| 身元保証人の不在 | 21.4% |
① 国土交通省の実務調査(2025年)
- 出所:国土交通省『高齢者の建物賃貸借契約における実務上の課題』
- 内容:賃貸人の約7割が高齢者の入居に対して拒否感を示しており、その理由の約9割が「居室内での死亡事故等に対する不安」
- リンク:国土交通省の調査報告書(PDF)
② 民間調査:株式会社R65による実態調査(2025年)
- 出所:株式会社R65『高齢者の住宅難民問題に関する実態調査(2025年)』
- 内容:65歳以上の約3人に1人(30.4%)が年齢を理由に賃貸住宅への入居を断られた経験あり。直近1年では36.7%に上昇
- リンク:R65のプレスリリース(PR TIMES)
これらの調査は、制度整備が進む一方で、現場の実態として高齢者の“借りづらさ”が依然として根強いことを示しています。
このような状況の中、政府や自治体による高齢者向け住宅支援の取り組みも進められてはいますが、まだ十分とは言えません。(【高齢者の住宅弱者改善】「高齢者歓迎」の賃貸住宅、数年で2倍超 「受け入れは社会的責任」毎日の記事から考えてみよう【気になる記事ブログ㉝】)
2040年には単独世帯が全体の約40%を超えると予測されているにもかかわらず、社会的な受け皿は追いついていないのが現状です。
年金生活の現状
次に、年金生活への備えという視点があります。
公的年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、60歳からの繰り上げ受給も可能です。ただし、受給額は減額されます。
📈 2025年度の年金受給額(平均)
- 国民年金(老齢基礎年金):月額 約57,600円
- 厚生年金(基礎年金込み):月額 約147,000円
📊 年金受給額の参考データ(2025年度)
| 年金種別 | 平均月額 | 出所 | リンク |
|---|---|---|---|
| 国民年金(老齢基礎年金) | 約57,600円 | 厚生労働省監修記事 | LIMOの年金解説記事 |
| 厚生年金(基礎年金込み) | 約147,000円 | 厚生労働省監修記事 | LIMOの年金解説記事 |
※上記は平均的な受給額であり、加入期間や収入により個人差があります。
この金額で生活を完結させるには、家賃の負担をできる限り抑える必要があります。
持ち家であれば、固定資産税や修繕費などはかかるものの、月々の家賃支払いが不要になることで、生活設計の安定につながります。
体力的な不安と住んでいる土地への愛着
さらに、体力的な問題もありました。
昨年の引っ越しは、これまでの10回の中でも最も負担が大きく、精神的にも肉体的にも限界を感じる場面が多くなりました。
「あと引っ越しできても2回が限界かもしれない」と思ったことも、家を購入する後押しとなりました。
そして最後に、今住んでいる土地への愛着です。
今住んでいる地域は街も人も穏やかで、暮らしやすさを日々感じております。
この土地の地域コミュニティの一員として、これからの人生を静かに紡いでいきたい——そんな思いが、家を買うという決断を前向きなものに変えてくれました。
今回の家を買う決断というのは、還暦という説目を迎え、年齢や年金想定という消極的な理由が背中を押したのが現実です。
還暦という節目は、人生100年時代と言われる現代においても、なお社会的な意味を持つ年齢です。
働き方、住まい方、地域とのつながり——それらを見直すタイミングとして、還暦は静かに人生の方向を問い直す機会となりました。
Views: 10