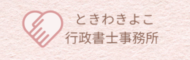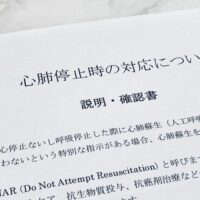- Home
- 話題の映画・ドラマ・アニメブログ, 連載シリーズ
- 血筋は法か、呪縛か——映画「国宝」から芸能の系譜をめぐる思索
ブログ
8.202025
血筋は法か、呪縛か——映画「国宝」から芸能の系譜をめぐる思索

第一章 伝統芸能と“血の記憶”——映画『国宝』を観て感じたこと
歌舞伎の舞台には、目に見える技だけでなく、目に見えない記憶や精神が受け継がれている気がします。映画『国宝』は、そんな舞台の深層を描いた作品でした。美しくて残酷で、少し怖いくらいに人間の覚悟が滲んでいたように思います。
吉沢亮さんと横浜流星さん演じる二人の役者は、まさに「血を超えようとする者」と「血に守られる者」でした。才能は血筋に勝つことができる——でも、その代償は大きい。家族、健康、時間…時には自分自身すら失うほど。芸能の世界では、その“喪失の重み”が美しさに昇華されていて、観る者はただ息を呑むしかありません。
血筋とは、単なる遺伝のことなのでしょうか。映画を観ながら、私は「血筋は記憶の器かもしれない」と思いました。技術だけでなく、芸の意味、気配、所作の理由——そういったものが、黙って受け継がれていく。そこに“家”や“家系”という言葉が宿るのだとしたら、それは法制度だけでは語りきれないものです。日本の民法は、戦後に家制度を廃止し、戸主という概念も無くしました。今は夫婦と未婚の子を基本とする核家族が標準です。でも、たとえば相続や成年後見、死亡届の提出など、私たちの日常を支える制度の中には、今もなお“血族”が優先される場面が多くあります。直系の家族には遺留分がありますが、傍系の兄弟姉妹にはそれがありません。それでも制度の中では、親族と他人の間に大きな隔たりがあります。それはもしかしたら、制度が変わった後も、私たちの中に“血の記憶”が生き続けているからなのかもしれません。芸能の世界では、それが露わになります。芸に人生を捧げることは、血を超える挑戦であり、同時に血に守られた継承でもある。その矛盾と緊張の中に、人間の美しさと脆さが浮かび上がってくるように思われました。
第二章 家制度の終焉と、消えなかった“家”のかたち
戦後の民法改正によって、長く続いた家制度は廃止されました。戸主という役割はなくなり、「家」ではなく「個人」が法律の単位になったのです。夫婦と未婚の子を中心とした核家族が標準となり、家名を継ぐという考え方は制度の外へと押し出されました。
でも、それで本当に「家」は無くなったのでしょうか。
芸能の世界を見てみると、そう簡単に“家”が消えるとは思えません。たとえば歌舞伎や能では、家系による継承が今も強く生きています。芸名には家名が宿り、親から子へと技術や心構えが手渡されていく。それは法的な「家族」とは違いますが、文化的な「家」——つまり記憶と責任の連鎖としての家——が、しっかりと根を張っているのです。
家制度が消えても、人は“家族らしさ”に救われようとします。介護や相続、死後の事務など、人生の節目ではやはり家族的なつながりが求められる。成年後見の申し立ては血族・姻族に限られ、死亡届の提出も親族であることが原則。相続では、遺留分が保障されるのは直系の家族だけです。制度の言葉こそ変われど、“血族を中心にした社会のかたち”は根底で生き続けているように感じます。それに比べて、芸能の継承にはもっとあからさまな“血の論理”があります。なぜ芸能では血筋が重視されるのか。その理由は、単なる遺伝の話ではなく、“身体に染み込んだ文化”をどう受け継ぐかという問いにあります。幼い頃から舞台裏にいた者が、自然と身に着ける所作や気配。それは教えられるものではなく、“共に生きる”ことで染み込んでいくものです。
法が「家」を手放したあと、芸能は「家」を記憶として残したのかもしれません。そして私たちの日常の制度もまた、どこかで「家族」や「血縁」という見えない地図に沿って動いている。
家制度が終わったはずの社会に、なぜこんなにも“家の記憶”が残っているのか。それを考えることは、今の社会で何を「つなぐこと」に意味があるのかを問い直すことでもあります。
そしてそれは、芸能が問い続けてきた「何を継ぐのか」「誰が継ぐのか」という命題と、静かにつながっているように思うのです。
第三章 継承と喪失——法と感情が触れられないものについて
継承とは、いつも「何かを残すこと」と思われがちです。財産や名前、役割や義務。法の世界では、それを明確に定義することで社会の秩序が保たれています。相続にはルールがあり、後見制度には申し立ての資格があります。誰が何を引き継ぐか——それは、制度によって整理されているのです。
けれども、人が本当に継いでいるものは、そんなにはっきりした形ではないのかもしれません。
感情の継承——それは、記憶の染み、言葉にならない想いの連鎖。ときに、血のつながりよりも深く、制度では測れない結びつきとなって人の心に宿ります。
映画『国宝』に描かれていた喜久雄と俊介の20年は、「継ぐ」という言葉では語れない時間でした。若くして頂点を掴んだふたりが、長い歳月のなかで味わった孤独と絶望。世界に拒まれ、他者とすれ違い、自らを削っていったその過程は、継承というよりも“喪失”の連続だったようにも見えます。芸の世界では、継承が“温もり”を伴うとは限りません。むしろ、すべてを差し出し、自分自身すら手放した先にしか芸の形が現れない。俊介が足を失い、喜久雄が家庭を失い、そのすべてを踏み台にして舞台に立つとき、彼らが背負っていたものは法でも感情でもなく、“焼け残った自己”だったのかもしれません。
制度の中での継承——たとえば遺産相続や親族制度は、守られるべき枠組みとして存在します。でも、その枠の外で、人はどこかで別のものを継いでいます。芸のように、美しさのために自己を燃やすような継承。それは誰にも渡すことのできない、孤独な遺産であり、誰にも測ることのできない、人間の痕跡です。
感情も、法も、そこには触れられない。
それでも、誰かが見てくれた舞台の一瞬には、その喪失が焼き付いている。
継承とは、たぶん、そういうものなのかもしれません。
今回の映画の舞台は芸能というある種特殊な世界であり、一般家庭とは異なります。しかし、血筋の優位さ、血筋の残酷さ、など血筋にまつわる様々な側面をみることができました。
「血筋か才能か?」、努力と運、誰と巡り合うのか、人生は複合的ですし、まさに人生は「禍福は糾える縄の如し」
Views: 132