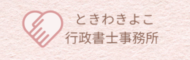- Home
- 地域共生社会, 話題の映画・ドラマ・アニメブログ, 認知症・成年後見制度
- 『90歳。何がめでたい』を観て ――尊厳ある老いと意思決定支援について考えてみよう【話題の映画・ドラマ・アニメから考えるブログ56】
ブログ
9.102025
『90歳。何がめでたい』を観て ――尊厳ある老いと意思決定支援について考えてみよう【話題の映画・ドラマ・アニメから考えるブログ56】
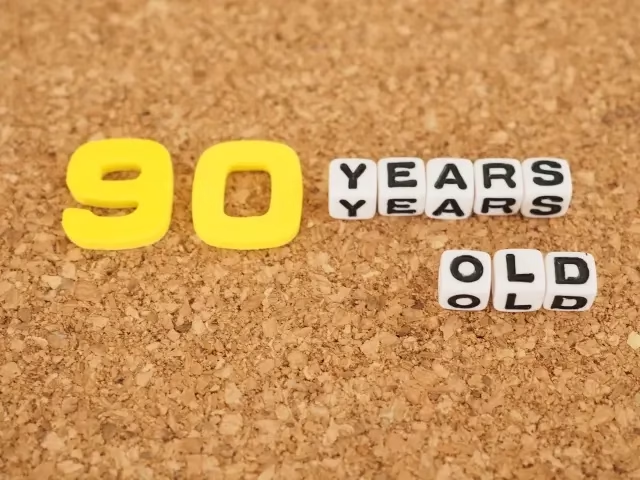
映画の概要とあらすじ
『90歳。何がめでたい』は、作家・佐藤愛子さんの同名エッセイを原作とした映画です。2024年6月21日に劇場公開されました。90歳を迎えた佐藤さんが、世の中の風潮や老いに対する違和感を、痛快かつユーモラスに語る姿が描かれています。この映画は、前田哲監督がメガホンを取り、大島里美が脚本を担当しています。そして主演は大女優、映画公開時90歳の草笛光子さんが演じています。
90歳を過ぎた作家・佐藤愛子(草笛光子)は、断筆宣言をしてからは鬱々とした日々を過ごしていました。そんな彼女のもとに、中年の編集者・吉川(唐沢寿明)がエッセイの執筆依頼を持ち込んできます。愛子は、生きづらい世の中への怒りをユーモアを交えてエッセイに綴り、そのエッセイが大反響を呼びます 。
映画は、愛子の人生が90歳にして大きく変わり始める様子を描いており、彼女の家族や周囲の人々との関わりも描かれています 。編集者・吉川の妻・麻里子(木村多江)や愛子の娘・響子(真矢ミキ)、孫・桃子(藤間爽子)など、多彩なキャストが登場します 。
後見業務、福祉業務の中での意思決定支援という考え方について
以前ブログでも意思決定支援について何度か触れておりますが、私が高齢者の方と接する時強く意識しているのが「意思決定支援」という考え方です。これは、認知症や障害などにより判断能力が低下した方が、自らの意思を形成・表明し、選択できるように支援することを指します。
平成29年の「成年後見制度利用促進基本計画」以降、後見人は単なる代理人ではなく、本人の意思を引き出し、実現を支援する伴走者としての役割が求められるようになりました。
🧭 意思決定支援の法的根拠とその意義
意思決定支援は、本人の意思を最大限尊重しながら、必要な支援を提供する仕組みです。以下の法制度がその根幹を支えています。
🔹 関連法制度と根拠
- 成年後見制度(民法第7条~第13条)
判断能力が不十分な人に対し、後見人等が法的代理を行う制度。意思決定支援の一環として、本人の意思を可能な限り反映することが求められています。 - 障害者総合支援法(第4条)
障害者が自立した生活を営むために、意思決定支援を含む支援を提供することが規定されています。 - 介護保険法(第5条)
高齢者が尊厳を保持しつつ自立した生活を営むことを目的とし、意思決定支援はその実現手段の一つです。
映画の中で佐藤さんは、自分の意思を明確に語り、周囲に遠慮なく伝えることができていました。しかし、現実の高齢者の多くは、自分の希望を口にすることにためらいを感じています。だからこそ、支援者は「語られない意思」に耳を澄まし、「語ることへの勇気」を支える必要があります。
意思決定支援とは、法的な選択肢を提示することではなく、本人の過去の価値観や生活歴を踏まえた「その人らしい選択」を支える営みです。それは、制度の枠を超えた、人間的な支援のかたちでもあります。
老いる中で若い世代の交流と家族以外の他者との交流のもたらす恩恵について
映画の中で印象的だったのは、佐藤さんが編集者や家族以外の人々と積極的に関わっていたことです。唐沢寿明さん演じる編集者とのやりとりは、時に衝突を生みながらも、佐藤さんの生活に外の視点をもたらし、日常にリズムと刺激を与えていました。
高齢者が家族の中だけで過ごすのではなく、若い世代や他者と関わることで、関係性が健全に保たれることがあります。福祉の現場でも、支援者や地域の人々が「第三者」として関わることで、家族の閉塞感が和らぎ、本人の意思がより自由に表現される場面が生まれます。
家族は制度ではなく関係性であり、その関係性は、時に外からのまなざしによって呼吸を取り戻します。老いの中にある孤独や閉じた関係性をほぐすために、他者の介入は欠かせない要素だと感じます。日本では介護や福祉の公的なサービスが色々あります。もし、介護や福祉でお悩みの方は、地域包括支援センターに足を運ばれることをおすすめします。
🤝 他者の存在が孤独を和らげる──統計から見える関係性
内閣府が令和6年に実施した「人々のつながりに関する基礎調査」では、相談相手の有無と孤独感の関係が明らかにされています。
📊 クロス表:相談相手の有無と孤独感の関係
| 相談相手の有無 | 「孤独をしばしば・常に感じる」と回答した割合 |
|---|---|
| いる(89.6%) | 4.1% |
| いない(10.4%) | 19.5% |
この表から読み取れるのは、相談相手がいない人は、いる人の約5倍の割合で強い孤独感を抱えているという事実です。つまり、制度的な支援だけではなく、心理的なつながりや信頼関係の構築が、本人の感情や生活の質に深く関わっているのです。
尊厳ある老いとは
佐藤さんの姿を通じて、私は「尊厳ある老い」とは何かを改めて考えました。それは、過去の功績によって尊敬されることではなく、今をどう生きるかという姿勢にこそ宿るものかもしれません。
佐藤愛子さんは、常に自分の意思を明確に伝え、周囲を圧倒するほどの存在感を放っていました。編集者に対しても、家族に対しても、遠慮なく「自分の考え」を語る姿は、痛快でありながら、どこか羨望のまなざしを誘います。しかしそれは佐藤愛子さんが、大家であり、90歳を超えても編集者が高級な手土産を持って連載をお願いされる立場であり、稀有な高齢者です。
現実の一般の高齢者の多くは、そうした「自己表明」にハードルを感じているのではないでしょうか。自分の希望を口にすることで迷惑をかけるのではないか、わがままだと思われるのではないか――そんな遠慮や不安は自分の身の回りの高齢者と話していても感じます。
福祉や後見の現場でも、尊厳ある老いを支えるためには、制度の枠を超えたまなざしが必要です。本人の言葉にならない思いに耳を傾け、制度の中に「余白」をつくること。それが、支援者としての責任でもあると感じます。
佐藤愛子さんは現在101歳を迎えられています。まさに人生100年時代の先駆者です。今後のご活躍をお祈り申し上げます。
Views: 16