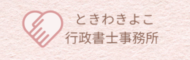ブログ
2.202026
「内館牧子が終活しない理由|定年は生前葬?氷河期世代の行政書士が考える老後のリアル」

はじめに
冬の凛とした空気の中、ふと本棚に目をやると、一際強いエネルギーを放っている一角があります。そこには、脚本家であり、作家であった内館牧子さんの著書が並んでいます。
先日、内館牧子さんの訃報に接しました。三菱重工のOLを15年務めてから脚本家の道へ進み、『想い出にかわるまで』や『ひらり』、そして大河ドラマ『毛利元就』など、特に女性の心理に深く踏み込んだ名作を次々と世に送り出した彼女。私の青春時代、テレビから流れる生々しくも痛快なセリフに、どれほど刺激を受けたことでしょう。
今回は、心からの敬意を込めて、内館さんが描き続けた「老いのリアル」と、彼女がなぜ最後まで「終活」を拒み続けたのか。そして、終活の専門家である私との価値観の違いから見える「人生の幕引き」について綴ってみたいと思います。
1. 「きれいごと」を剥ぎ取る、内館脚本の衝撃
内館さんの作品には、常に「剥き出しの人間」がいました。 かつてのドラマでは、姉妹で一人の男性を奪い合ったり、母親と娘が一人の男を激しく取り合ったりと、世間体が良しとする「美しい家族像」を木っ端微塵にするような、生々しい会話が飛び交いました。
劇中で放たれた「盛りのついた雌豚」という、耳を疑うような強烈な言葉。あるいは、『出会った頃の君でいて』の中で描かれた、「金持ちならバカでもいいと思ってた。でも、そんな女じゃつまらないんだ」
これらは単なる毒舌ではなく、人間が持つ「業(ごう)」を美化せず、ありのままに見つめる内館さんなりの誠実さだったのではないでしょうか。既存の枠の中でもがき、思いもよらなかった結末や関係性に辿り着く人々の姿に、私たちは「きれいごとではない真実」を見て、深い溜息と共感をついてきたのです。
2. 「定年は生前葬」—— 突きつけられた老いのリアル
脚本家として一時代を築いた後、東北大学の大学院で相撲を研究し、女性初の横綱審議委員を務めるなど、そのキャリアは多岐にわたりました。そんな彼女が晩年に手掛けた「高齢者小説シリーズ」は、私たち「終活」に携わる者にとっても、避けては通れない問いを突きつけました。
特に、第1作『終わった人』で主人公が放った一言。 「定年って、生前葬だよな」
この言葉は、定年を間近に控えた方、あるいは迎えたばかりの方にとって、どれほど残酷で、それでいて「言い当てられた」と感じさせる響きを持っていたことでしょう。社会的な役割を終え、居場所を失う喪失感。内館さんは、世間が語る「悠々自適なセカンドライフ」という言葉の裏側に隠された、ヒリヒリするような孤独を白日の下にさらけ出したのです。
3. なぜ、内館牧子は「終活」を拒んだのか
終活に携わる専門家として、私が最も背筋が伸びる思いで拝読したのが、内館さんの「終活に対するスタンス」です。内館さんは生前、インタビューや著書の中で、「終活なんて一切しない」と公言されていました。
心臓弁膜症で九死に一生を得るという経験をされながらも、その考えは揺らぎませんでした。PHPのインタビュー記事で死に関する内館さんの記述があります。「 でも倒れる寸前「しまった、月謝が無駄になった」とか「モノがごちゃごちゃ。身辺整理しときゃよかった」などと後悔したかといえば、そんなことを考える間もありませんでした。もし意識不明のままで死んでいたとしたら、自分が死んだことさえ気がつきません。いろんな死があるでしょうが、多くは何もわからないんじゃないかしら。」
「死ぬ準備をする暇があるなら、大学院にでも行って勉強しろ」とはっぱをかける姿は、まさに最後まで現役であり続けた彼女の魂の叫びでした。
ここで、世代背景の違いが見えてきます。 内館さんは団塊の世代。拡大し続ける社会の中で、常に「何者か」であろうと戦ってきた世代です。彼らにとって人生は「使い果たすもの」であり、終わりの準備をすることは、自らの生命力を否定することに等しかったのかもしれません。テレビ「徹子の部屋」で内館さんはOL時代居心地は悪くなかったけれど自分の居場所ではなかった。脚本家になって自分の居場所を見つけたと言っていました。
対して、就職氷河期世代である私たちは、常にリスクを管理し、周囲に迷惑をかけないことを最優先に教え込まれてきました。私たちが考える終活は「責任ある幕引き」であり、内館さんのそれは「最後の一滴まで燃え尽きること」だった。この違いは、どちらが正しいというものではなく、生きてきた時代の空気の違いなのだと感じます。
4. 終活の専門家として思うこと
「終活が老人の気力を奪う」 内館さんのこの指摘は、専門家である私への「劇薬」のような教えです。 確かに、ただ持ち物を捨て、関係を整理し、死を待つだけの準備は、寂しさを募らせるだけかもしれません。
しかし、私はこうも思うのです。 行政書士としてお手伝いする書類の先には、必ずその方の「生への想い」があります。 「家族を困らせたくない」という優しさも、内館さんのように自分の生を生き切る姿勢も、形は違えど、どちらも自分の人生を愛しているからこそ生まれる願いではないでしょうか。
たとえ書類上の準備はしなくても、内館さんのように「自分の居場所」を探し続け、大学院に行き、毒を吐きながらも全力で走り抜ける。その生き様自体が、残された人々への最大の「遺言」となり、最高の終活になることもあるのでしょう。
おわりに
内館牧子さんという大きな星が、夜空から姿を消しました。多感な10代から体力が衰えつつある50代まで一貫して内館さんの言葉に心が震え激しく揺れました。そして潔い生き方に勇気をもらいました。
私が提供する「終活」は、内館さんの考えとは対極にあるかもしれません。しかしいつか内館さんの言葉が今よりもっとわかるときがくるかもしれません。 たくさんの痛快な言葉を、本当にありがとうございました。 新しい言葉を聞くことはできませんが、遺された数々の小説をこれから読み返し、私も命を燃やしていきたいと思います。
Views: 0