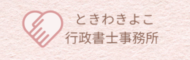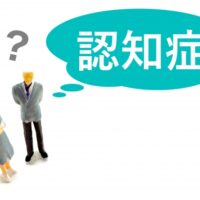- Home
- 気になる記事ブログ, 認知症・成年後見制度
- 【補聴器は残存能力の活用】筆者の母親が集音器から補聴器を身に着けるまでの実記録→耳の遠くなった高齢の親に補聴器を贈った、オリラジ藤森さんの記事から考えてみよう(続編)【気になる記事ブログ31】
ブログ
1.302025
【補聴器は残存能力の活用】筆者の母親が集音器から補聴器を身に着けるまでの実記録→耳の遠くなった高齢の親に補聴器を贈った、オリラジ藤森さんの記事から考えてみよう(続編)【気になる記事ブログ31】

【補聴器は残存能力の活用】筆者の母親が集音器から補聴器を身に着けるまでの実記録→耳の遠くなった高齢の親に補聴器を贈った、オリラジ藤森さんの記事から考えてみよう(続編)【気になる記事ブログ31】
2023年6月にオリラジ藤森さんが高齢の親に補聴器を送った記事を書きました。その中で筆者の母親に集音器を贈った事を記載しましたが、その後母親の聴力が低下し、対面での会話、ビデオ通話での会話に齟齬が生じることも多くなり、集音器を贈った一年半後に、補聴器を買うことになりました。今回は、購入店の選び方、補聴器の選び方、家族内での合意形成、補聴器に後ろ向きだった母親が積極的に補聴器を身に着けるまでの過程について書いていきたいと思います。
- 補聴器購入までの道のり
- 補聴器の購入店の決め手は、家から近い、お店の人が親切、定期的なメンテナンスで安心安全
- 家族の合意や積極的な後押しがないと、高齢者が補聴器を買うのは難しい
- 残存能力の活用として補聴器を考えてみませんか
それぞれ一つずつみていきたいと思います。
補聴器購入までの道のり
2023年6月に耳の聞こえが悪くなってきた母親に集音器をプレゼントしました。当初は積極的に使用していましたが、たまに装着時に「ピーン」という甲高い金属音が鳴るなど不具合が生じるようになり、集音器は日常的に装着するものではなく、友人との食事やお出かけ、旅行など特別な行事に時に使用するものとなっていきました。ネットで購入したものだったため、使い方やメンテナンス方法などは取り扱い説明書などを自分で確認する必要があり、不具合が生じた際の対応も高齢者には面倒なため(私たちも知識を持ち合わせておらず)、徐々に使われなくなっていきました。
2024年に入り、同居する父親、離れて住む姉からも母親の耳が聞こえておらず、会話が、成立しないという話が出てきました。相手の話している途中でも遮って自分の話をしたり、こちらの話に同意しているように何度も頷くけれど、頷いた内容がわかっていないことも多くなってきました。2024年11月に私の夫から補聴器を提案され、それまでは頑なに補聴器を拒否していましたが、まずはお店に行くことを了承し、2024年の12月初旬に補聴器専門店に行き、機種を変えて二度、二週間に渡るトライアル装着期間を経て、2025年1月に購入を決め、2025年1月下旬に補聴器が出来上がりました。
補聴器の購入店の決め手は、家から近い、お店の人が親切、定期的なメンテナンスで安心安全
補聴器を購入した話をする際に、お店はどうやって決めたのか、補聴器の種類はどうやって決めたのか周囲から聞かれることもありましたが、集音器購入での反省を生かして、今回の補聴器購入では以下3点を基準に、加えて聴覚に関する専門家、認定補聴器技能者がいる専門店を探しました。
- お店が家から近く、わかりやすい場所で通いやすい
- お店の人が親切で、高齢者が安心して通える場所
- 定期的なメンテナンスがあり、困った際にすぐ対応してくれる
まとめると、安心補聴して器を購入し、母が補聴器を使用中、継続的にフォローして安全に補聴器が使えるお店です。また補聴器を調べるうちに、認定補聴器技能者という資格があることを知り、上記の条件に加えて認定補聴器技能者がいるお店を探しました。
■認定補聴器技能者とは
認定補聴器技能者とは、補聴器の販売や調整などに携わる人に対し、公益財団法人テクノエイド協会が、厳しい条件のもと、基準以上の知識や技能を持つことを認定して付与する資格です。
また、実際に初回訪問から購入までの流れをみていきたいと思います。
以下は補聴器技能協会のHPから抜粋した流れとなります。
1-1:事前のコンサルティング
- 補聴器を使用したい動機、場などをヒアリングして、目標を設定
1-2:補聴器を合わせるための聞こえの測定
- 音の聞こえを測定
- ことばの聞き取りを測定
1-3:補聴器の選択
- 聞こえの測定結果、お客様の主な訴えや希望、耳の状況、身体的状況などにより複数の機器から、補聴器と関連機器を選択し提案
1-4:補聴器の調整
- 補聴器から出力する音の大きさを考えた上で、いろいろな方式より選択し調整
- テレビを見るとき、電話を聞く時など、状況に応じたプログラムを設定
1-5:補聴器の効果測定
- 補聴器を装用した状態で聞こえを測定し、ことばの聞き取りなどを評価
1-6:補聴器特性の測定
- 使用時の周波数特性の評価と記録
1-7:補聴器装用のケア
- お客様・ご家族への長期ケア
- 補聴器の管理や使用に関するトレーニング
- リハビリに関するアドバイスやコンサルティング
補聴器を取り扱っているお店は多数あります。また補聴器の値段も数万円から数十万にわたり多様な価格帯です。そのような多様な選択肢の中でお店や補聴器を選ぶには、ある程度優先順位を立てた方が良いかと思います。場所の近さを優先するのか、値段を優先するかなど、人それぞれ基準があると思います。私の場合は、安心と安全を第一に選びました。
また、購入に際して一番大事に考えたのは、母親の意思です。強制するのではなく、母親がどうしたいのか、補聴器が必要なのか、つけるとすればどの補聴器にしたいのか、母親自身の意思決定を尊重するように気を付けました。
家族の合意や積極的な後押しがないと、高齢者が補聴器を買うのは難しい
近年、前回のブログでも記載しましたが認知症と耳の聞こえの遠さとの関連なども指摘されており、補聴器の購入に対する関心は高まっていると推察されます。しかし高齢者が補聴器を購入するハードルはまだまだ高いと言わざるを得ないでしょう。
一つは、補聴器に対する思い込みや固定観念、自分にはまだ早すぎるのではないかという購入者がなかなか積極的になれないことです。またもう一方では補聴器購入を家族に反対されるケースです。
既に補聴器を複数台購入しており、しかし聞こえが改善せず、買っても使用していないケースでは、更なる補聴器の購入を散財と認識する場合もあります。
補聴器は数万円から数十万円という価格帯に幅があり、決して安い買い物ではありません。むしろ高い買い物となります。家族が補聴器の購入に関して消極的になることも当然あるでしょう。
しかし、現在は人生100年時代と言われ、老後はこれから一層長くなるのです。人生80年と言われていた時代であれば、補聴器の耐用年数の前に自分の寿命が尽きるケースもあったでしょうが、なるべく快適に、楽しく、元気に自立して人生を過ごすために、ご家族の方も補聴器という選択肢を考えてみてはいかがでしょうか。
残存能力の活用として補聴器を考えてみませんか
デンマークで生まれた介護の3原則があります。1982年にデンマークのベント・ロル・アナセン氏が提唱し、高齢者福祉の三原則と呼ばれています。
- 生活の継続性
- 自己決定の尊重
- 残存能力の活用
失われつつある聴覚をサポートする器具が補聴器です。そのように考えると補聴器は、まさに残存能力の活用を促進する機器でもあります。
これから、恐らく老後は今の私たちが考えるようもっとずっと長くなると予想されます。その時期を自分なりに楽しく快適に過ごすためにも、失われつつある機能を他のやり方で補完できるのであれば、色んなやり方を試してみてはいかがでしょうか。
母親が購入した補聴器は、とても小さく一見しただけでは補聴器を使用しているかどうかわかりません。また音量はお店のアプリで調整するため、装着側での調整が不要です。定期的に音量の調整もしてくれるそうです。科学技術の進歩はすさまじいです。
消耗品で耐久年数は5年程度のため、故障する可能性もあります。しかし、母親はテレビの音量が小さくなり、家のチャイムの音が聞こえるようになり、家族や友人知人とスムーズに会話ができるようになり、とても喜んでいます。
補聴器が母の日常になるかどうかはこれから見守りが必要ですが、もし補聴器の選択を考えているのであれば、まずは相談してみてはいかがでしょうか。人生100年時代ですから。
実際の補聴器になります。右耳が赤で左耳が青です。とてもコンパクトで性能は抜群です。
Views: 97